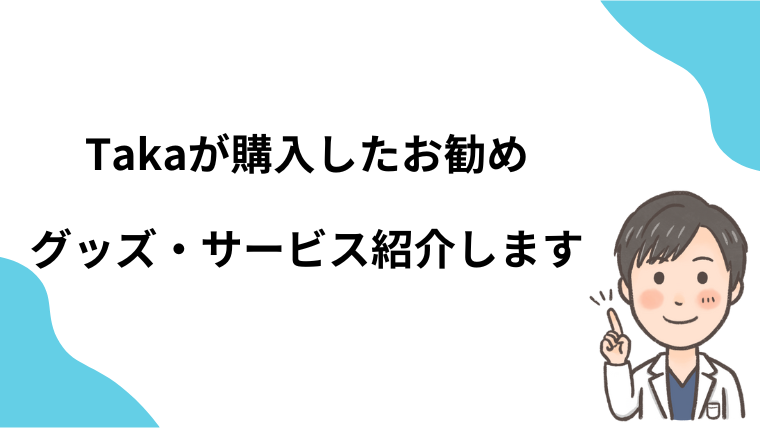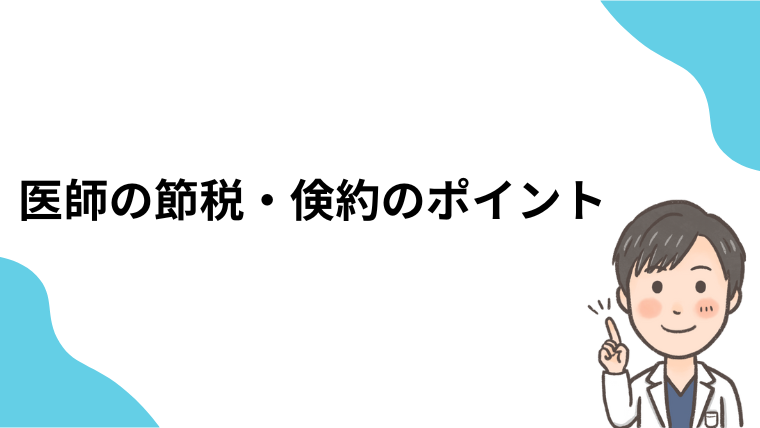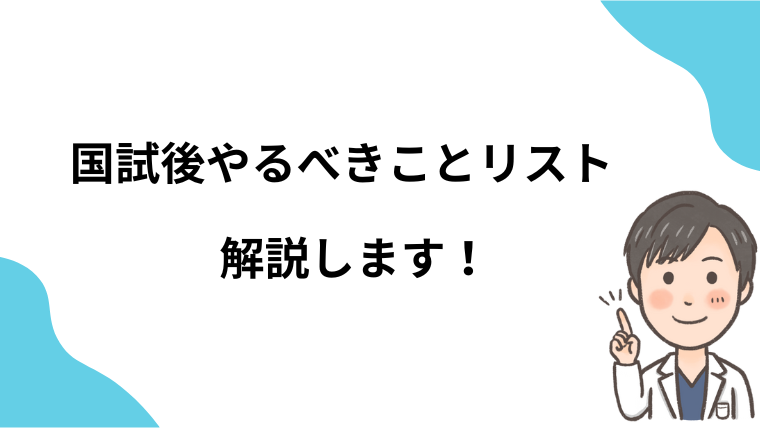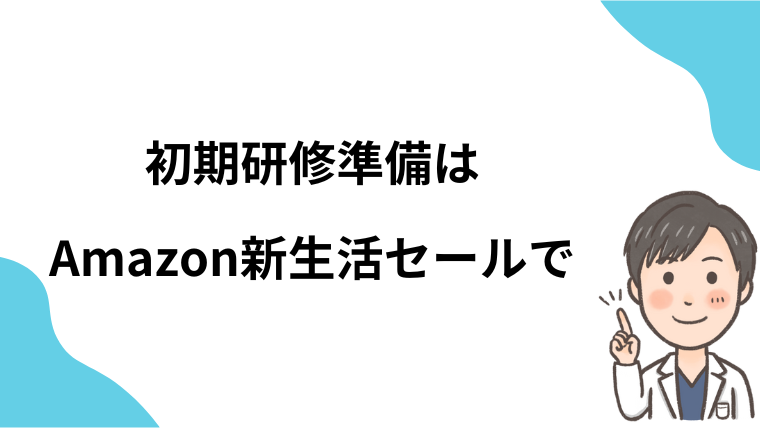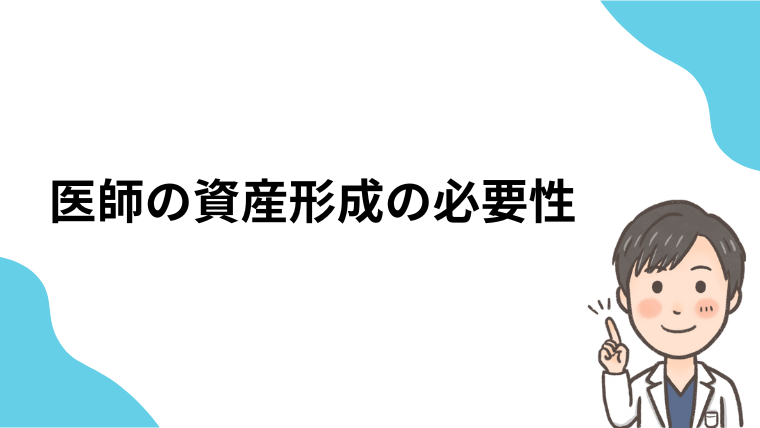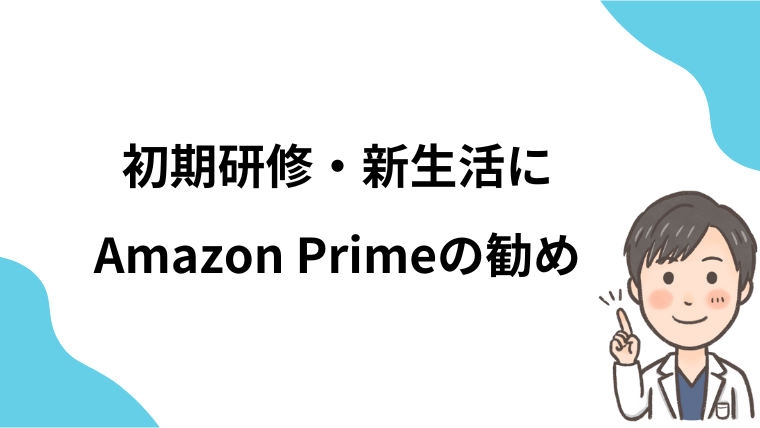医師向け】税金で手取りが減る理由とは?知らないと損する税金の基本
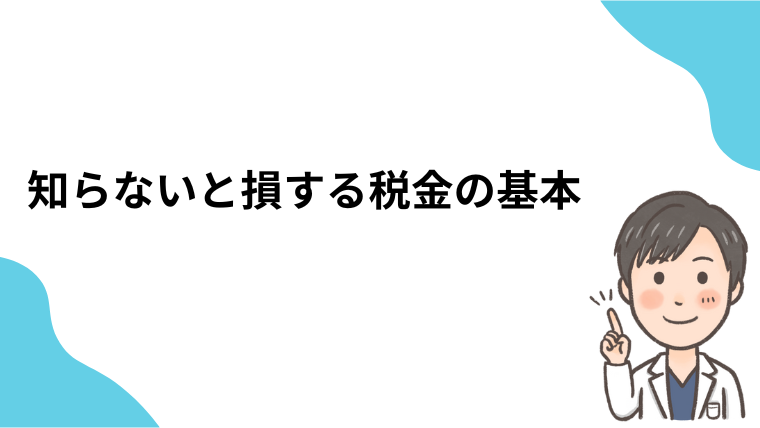
はじめに
こんにちは。今回は「医師が知らないと損する税金の話」についてお届けします。
専門医試験のために更新が途絶えていましたが、再開していこうと思います。
医師は一般的に高収入の職業ですが、意外と「税金のしくみ」をしっかり理解していない方も多い印象です。
「こんなに働いてるのに、思ったよりお金が残らない…」と感じたことはありませんか?
そのモヤモヤの正体は、税金と社会保険料にあることがほとんどです。
この記事では、医師が知っておくべき税金の基本と、手取りを少しでも増やすための考え方をわかりやすく解説していきます。
医師の給与から引かれているものは?
医師の給与明細を見ると、毎月の給料から次のような項目が引かれています:
- 所得税
- 住民税
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
これらを合計すると、額面の25〜40%が引かれることも。
医師の給与明細を見てみよう(ざっくりイメージ)
勤務医(年収1,200万円/月収100万円)の給与明細の一例を見てみましょう。
| 項目 | 金額(例) |
|---|---|
| 支給額(総支給) | 1,000,000円 |
| 所得税 | 90,000円 |
| 住民税 | 75,000円 |
| 健康保険 | 45,000円 |
| 厚生年金 | 70,000円 |
| 雇用保険 | 3,000円 |
| 手取り | 約717,000円 |
これだけ引かれて、手元に残るのは7割程度。
「なんとなく税金が高い気がする…」と感じるのも当然かもしれません。
所得税ってどうやって決まるの?
所得税は「課税所得」に対してかかる税金で、収入が高くなるほど税率が上がる「累進課税制度」が使われています。
ざっくり言うと、所得が多い人ほど税金が重くなる仕組みです。
例えば、課税所得が900万円を超えると23%、1,800万円を超えると33%の税率がかかってきます。
ただし、これは「年収」ではなく「課税所得」に対してなので、各種控除(基礎控除、社会保険料控除など)を引いた後の金額で計算されます。
住民税は一律10%。でも意外と重い!
住民税は、所得の10%前後が課されるシンプルな仕組みです。
ただし、ここで注意が必要なのは「前年の所得に対して課税される」という点。
つまり、副業やスポットバイトで収入が増えると、翌年の住民税がドンと増えることもあります。
しかも、住民税の通知が自宅に届くことで「副業がバレる」リスクもあります。
副業をしている方は、住民税の申告方法(特別徴収 or 普通徴収)にも気をつけましょう。
申告方法について詳しくは次で説明します。
副業がバレないようにするには?
副業をしている医師が気になるのが「職場にバレないか?」ということ。
じつは住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」にすることで、職場に副業収入が知られるリスクを減らすことができます。
確定申告の際に「住民税の徴収方法を自分で納付にする」にチェックを入れるだけ。
これだけで、住民税の通知が勤務先に届かなくなるので、副業を始めたい人には必須の知識です。
社会保険料も収入に応じて上がっていく
勤務医は「厚生年金」「健康保険」に加入しているため、これらの保険料も給与に比例して上がっていきます。
月収60万円以上あると、社会保険料だけで月10万円近く引かれていることも。
もし将来的にフリーランスや開業を考えているなら、自分でこれらの保険料を管理することになります。
今のうちから、しくみを理解しておくことが大切です。
税負担を軽くするためのヒント5つ
1. iDeCoやNISAを活用しよう
- **iDeCo(個人型確定拠出年金)**は、掛け金が全額所得控除され、節税しながら老後資金を準備できる制度です。
- 新NISAは、投資で得た利益が非課税になる制度。つみたて枠・成長投資枠をうまく使えば、大きな非課税メリットがあります。
とくにiDeCoは、高所得の医師ほど節税効果が大きくなります。
2. 控除をフル活用する
以下のような控除は、漏れなく使いましょう。
- 生命保険料控除
- 寄附金控除(ふるさと納税)
- 扶養控除(配偶者・子ども)
ふるさと納税は「実質2,000円」で返礼品がもらえる上に、税金が控除される仕組み。
医師のような高所得者にとって、特にお得な制度です。
3. 副業や開業で「経費」が使える立場に
勤務医は原則「経費」が使えませんが、副業や開業によって個人事業主になれば、
学会参加費・書籍代・通信費・パソコン代など、さまざまな支出を経費として扱えるようになります。
経費が増える=課税所得が減る=税金が減る、という流れになります。
4. 確定申告を味方につける
スポットバイトや原稿料など、給与以外の収入がある場合は、確定申告が必要です。
医師の中には「申告しなくてもバレない」と思っている方もいますが、基本的にバレます(マイナンバー制度の普及により、情報が自動で紐づけられます)。
還付を受けたり、控除を適切に使ったりするためにも、毎年しっかりと申告する習慣をつけましょう。
5. 会計ソフトや専門家をうまく使う
副業や事業所得が増えてきたら、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを導入するのがおすすめです。
また、税理士さんに相談することで、節税のヒントやリスク回避のアドバイスももらえます。
まとめ|「知らない」は最大のコスト
医師という職業は、専門性が高く忙しい分、お金の知識は後回しになりがちです。
でも、税金のしくみを知るだけで、手取りが増えたり、お金が貯まりやすくなったりするのは事実です。
まずは「自分が何をどれだけ払っているのか?」を知ることから始めてみてください。
そして、今日の内容のどれか一つでも、実生活に活かしていただけたら嬉しいです。
よくある質問・FAQ
Q. 医師でも経費って使えるの?
A. 給与所得だけでは経費計上はできませんが、副業や開業なら経費化は可能です。
Q. 副業をしていると何が変わる?
A. 税金は増えますが、同時に経費化や控除のチャンスが増えます。
Q. ふるさと税給はどのくらいお得?
A. 定められた上限円内なら、実質2,000円で返礼品がもらえるので得差感が高いです。